この記事では27卒や28卒向けにWEBテストの定番である玉手箱試験の言語の中でも難しい、論理的読解の過去問や練習問題、例題を会員登録なしで無料公開します。
玉手箱の論理的読解とはGAB形式の問題で、長文を読んで設問文の論理的な正誤を回答するタイプの問題です。
この玉手箱試験の論理的読解は慣れないと難しい問題なので、今回ご紹介する過去問や練習問題でしっかり練習し、本番に備えて頂けたらと思います。
玉手箱の言語の頻出問題集はこちらのアプリから行う事ができます。玉手箱の摸試が行えて10段階評価で行きたい企業のボーダーを超えてるか正確に自分の偏差値がわかるからおすすめです。こちらからインストールして活用してくださいね。
また、スマホでこのページを見てくださっている方限定で今まさに出題されている玉手箱の練習ができると評判のアプリを紹介します。
このアプリは玉手箱の練習だけでなく、10段階評価で自分の玉手箱の偏差値も出してくれて、志望企業のボーダーを突破できるのかも分かる便利アプリです。
この問題と「無料で手に入る玉手箱の問題集」だけやっておけばWEBテストは安心なので、スマホでこのページを見たこの機会に是非「玉手箱の練習ができると評判のアプリ」と「無料で手に入る玉手箱の問題集」を試してみてくださいね。

下記のURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!
自分の玉手箱の出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。
URLはこちら⇒https://lognavi.com/
\ 先ずはインストール /
玉手箱対策に時間をかけたくない場合は2月の今のうちに無料で手に入る玉手箱の解答集つき問題集をやっておくと就活が楽になりますよ。
▼25卒に大人気でした▼
今まさに出題されている玉手箱の問題があるのでチェックしておいてください。
上記の問題集は解答もあるので、正直解答集みたいなもので、あまり大声では言えませんが、26卒・27卒はこの解答を憶えれば勝てちゃいますね。
WEBテスト問題集公式⇒https://careerpark.jp/
\ 26卒・27卒に推奨 /
玉手箱の論理的読解の過去問や練習問題を公開
それでは早速玉手箱の論理的読解の過去問や練習問題を公開します。
玉手箱試験の難しいところは1問に避ける時間が短いところなので、とにかく問題の数をこなして慣れる事を心掛けましょう。
それでは問題を公開していきます。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題1
近年、多くの企業が「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」を経営戦略の一環として掲げている。これは、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向などにかかわらず、多様な人材を受け入れ、その能力を最大限に活用するという考え方である。企業がこのD&Iを重視する背景には、グローバル市場での競争力強化や、イノベーションの創出に対する期待がある。
従来の日本企業では、長期雇用や年功序列、同質性を重んじる文化が根強く残っており、D&Iの導入には抵抗感を持つ場合もあった。しかし、働き方改革や国際的な人権意識の高まりにより、そのような古い制度や価値観を見直す動きが強まってきている。
D&Iの推進には、単なる制度設計だけでなく、組織全体の意識改革も求められる。表面的な多様性だけを整えても、実際の職場環境が包摂的でなければ、真の意味でのD&Iは実現しない。リーダーシップのあり方やマネジメント手法も、多様性を前提としたものに変えていく必要がある。
このような観点から、D&Iは単なる人事戦略にとどまらず、企業文化そのものの再定義を迫るものであり、今後ますます重要性を増していくだろう。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)企業がD&Iを推進する主な目的は、国際的な人権意識の向上に対応するためである。
(2)D&Iの実現には、制度設計だけでなく、企業文化やマネジメントの改革も必要である。
(3)日本企業の多くは、今も年功序列や同質性を重視する文化を維持しており、それがD&I導入の障壁になっている。
(4)D&Iは制度整備だけにとどまる取り組みであり、職場環境の改善とは関係がない。
解答と解説を見る
(1)解答:C
本文では、企業がD&Iを重視する理由の一つに「国際的な人権意識の高まり」があるとは述べているが、主な目的がそれであるとは断定されていない。
(2)解答:A
本文に「制度設計だけでなく、組織全体の意識改革も求められる」と記述があり、正しいと判断できる。
(3)解答:A
本文には「長期雇用や年功序列、同質性を重んじる文化が根強く残っており…抵抗感を持つ場合もあった」とあるため、正しい。
(4)解答:B
本文には「実際の職場環境が包摂的でなければ、真の意味でのD&Iは実現しない」とあるため、誤り。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題2
新型コロナウイルスのパンデミックは、世界中の労働環境に大きな変化をもたらした。特にリモートワークの普及は、働き方そのものに対する価値観を大きく変える契機となった。多くの企業が出社型の勤務から在宅勤務へとシフトしたことで、通勤時間の削減や柔軟な働き方の実現など、働き手にとっての利点が明らかになった。また、家庭と仕事を両立しやすくなったという声も多く、育児や介護を抱える従業員にとっても歓迎すべき変化であった。
一方で、リモートワークには課題も存在する。対面でのコミュニケーションが減少することで、チーム内の連携や信頼関係の構築が難しくなるという指摘がある。また、業務の進捗管理や評価制度の見直しも必要になってきている。情報共有の遅延や孤立感の増加といった副作用も、徐々に顕在化しつつある。
このような変化に対応するためには、単なる勤務形態の変更にとどまらず、企業のマネジメントスタイルや組織文化そのものを柔軟に変革していく姿勢が求められている。今後、リモートワークと出社勤務を併用する「ハイブリッド型」の働き方が定着していく中で、いかにして社員のエンゲージメントを維持し、生産性を高めていくかが重要な経営課題となるだろう。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)リモートワークの普及によって、働き方の柔軟性が損なわれるようになった。
(2)リモートワークでは、チームの信頼関係を構築することが難しいという課題がある。
(3)ハイブリッド型勤務が生産性向上にどの程度貢献するかは、今後の研究結果を待たなければならない。
(4)リモートワークの導入は、単なる勤務形態の変更ではなく、企業の在り方そのものを問うものである。
解答と解説を見る
(1)解答:B
本文では「柔軟な働き方の実現など、働き手にとっての利点が明らかになった」と記載されており、逆の内容であるため誤り。
(2)解答:A
「チーム内の連携や信頼関係の構築が難しくなるという指摘がある」とあり、本文内容に合致する。
(3)解答:C
本文ではハイブリッド型勤務の生産性向上に関する明確な記述はなく、効果の程度については言及されていないため、判断できない。
(4)解答:A
「勤務形態の変更にとどまらず、企業の在り方そのものを問う」との記述があるため正しい。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題3
サステナビリティという言葉が広く認知されるようになった現在、企業は単なる利益追求だけでなく、環境や社会への責任も同時に果たすことが求められている。特に、気候変動への対応、生物多様性の保護、公正な労働環境の整備など、多岐にわたる課題に取り組む姿勢が、企業価値の評価基準として注目されている。
これに伴い、ESG投資(環境・社会・ガバナンスに配慮した投資)の市場も急拡大しており、投資家は企業の持続可能性に関する情報を重要視するようになった。従来の財務指標だけでなく、非財務情報の開示が企業にとって不可欠なものとなっている。
しかし、サステナビリティの実践は容易ではない。短期的な利益とのバランスを取る必要があり、経営判断の難易度は高まっている。また、単なるスローガンや表面的な活動ではなく、企業の根幹に組み込んだ実践が問われるようになってきている。
このような背景から、サステナビリティ経営はもはや一部の先進企業だけのものではなく、すべての企業にとっての新しいスタンダードとなりつつある。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)企業のサステナビリティ活動が従業員の満足度にどのような影響を与えているかは、明確ではない。
(2)非財務情報の開示は、企業にとってESG投資家へのアピール手段となっている。
(3)サステナビリティ経営は、一部の特定企業だけが対象となる経営戦略である。
(4)短期的な利益とサステナビリティの両立は、企業にとって困難な課題の一つである。
解答と解説を見る
(1)解答:C
本文では従業員の満足度に関する具体的な記述がないため、設問文の内容を論理的に導くことはできない。
(2)解答:A
「投資家は企業の持続可能性に関する情報を重要視するようになった」との記述から、非財務情報の開示が重要であることがわかる。
(3)解答:B
「サステナビリティ経営はすべての企業にとっての新しいスタンダードとなりつつある」とあるため、特定企業に限られるというのは誤り。
(4)解答:A
「短期的な利益とのバランスを取る必要があり、経営判断の難易度は高まっている」とあるため、本文と一致する。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題4
近年、地方創生が日本の社会的課題として注目されている。人口減少や高齢化が進む中、地方自治体や企業は、地域の活性化と持続可能な発展を目指して多様な取り組みを行っている。特に、都市圏からの移住促進やテレワーク環境の整備、地域資源を活かした観光開発などが推進されている。
地方創生の鍵となるのは、地域に根差した人材の育成と外部人材との連携である。UターンやIターンの動きも見られ、地域社会への新たな視点がもたらされている。一方で、行政主導の取り組みが必ずしも住民のニーズに合致しない場合もあり、地域コミュニティとの協働が成功の重要な要素となる。
また、地域経済を支える中小企業の支援も重要であり、デジタル技術を活用したビジネスモデルの転換や販路拡大などが求められている。特にコロナ禍以降、地域の課題がより顕在化し、地方創生の取組みは短期的なプロジェクトではなく、長期的な視点が不可欠であると認識されている。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)地方創生では、地域資源を活かした観光開発よりも、農業の近代化の方が主要な取り組みである。
(2)地方創生において、外部人材との連携が全く考慮されていない。
(3)地域経済の強化には、デジタル技術を用いたビジネス転換が求められている。
(4)地方創生の取り組みは、短期的な施策ではなく、長期的な視点が重要とされている。
解答と解説を見る
(1)解答:B
本文では「観光開発などが推進されている」と明記されているが、農業の近代化が主要な施策とは書かれていない。
(2)解答:C
本文には「外部人材との連携」が鍵とされているが、「全く考慮されていない」という設問には断定的すぎるため、導けない。
(3)解答:A
「デジタル技術を活用したビジネスモデルの転換や販路拡大などが求められている」と本文に記述されているため、正しい。
(4)解答:A
「短期的なプロジェクトではなく、長期的な視点が不可欠」と本文にあるため、本文内容と一致している。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題5
日本における企業の終身雇用制度は、長らく安定した雇用形態として評価されてきた。新卒一括採用に始まり、定年まで勤め上げるという働き方は、高度経済成長期における経済の安定と成長に寄与したとされている。しかし近年では、少子高齢化や経済のグローバル化、技術革新の進展などにより、雇用の在り方そのものが大きく見直されている。
一部の企業では、成果主義を導入し、年功序列型の賃金体系を廃止する動きもある。また、ジョブ型雇用の導入や、副業・兼業の解禁など、柔軟な働き方を取り入れる企業も増えてきている。こうした変化は、働き手のキャリア意識にも影響を及ぼしており、個人が自らのキャリアを主体的に設計する時代に移行しつつある。
一方で、依然として多くの企業ではメンバーシップ型雇用が主流であり、雇用制度の急速な変化に対して戸惑いや課題も少なくない。特に中高年層にとっては、新たな働き方への対応が困難なケースも見られる。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)近年の雇用制度の変化は、働き手が自らのキャリアを考えるきっかけになっている。
(2)現在の日本では、ジョブ型雇用が圧倒的に主流となっている。
(3)副業や兼業の実施率が全世代で急速に高まっていることが、本文からは明らかである。
(4)年功序列型の賃金体系は、見直しの動きが一部の企業で始まっている。
解答と解説を見る
(1)解答:A
本文に「キャリアを主体的に設計する時代に移行しつつある」とあるため、設問は正しい。
(2)解答:B
「ジョブ型雇用の導入企業が増えている」とはあるが、「圧倒的に主流」とは記載されておらず、誤り。
(3)解答:C
副業・兼業の「解禁」の記載はあるが、「全世代で急速に高まっている」との記述はなく、判断できない。
(4)解答:A
「成果主義を導入し、年功序列型の賃金体系を廃止する動きもある」とあり、正しい。
スマホでこのページを見ている方限定でお伝えしたいのが、今まさに出題されている玉手箱の問題が出ると評判の「Lognavi」というアプリです。
MBTI顔負けの性格診断も出来て、あなたの市場価値まで企業側に伝わって超大手優良企業からのオファーももらえちゃうから一石二鳥です!

下記のURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!
自分の玉手箱の出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。
アプリインストールはこちらから⇒https://lognavi.com/
※インストール後の初回起動はお早めに
\ 先ずはインストール /
ESや企業研究で玉手箱に時間を割く暇がないと思うので、今選考で出題されている玉手箱の練習が無料でできる玉手箱の無料問題集をやっておいてください。
無料でダウンロードできるので、玉手箱に時間をかけたくない場合は使ってみてください。
▼25卒に大人気でした▼
参考書や問題集と違って問題が最新版にアップデートされるので、今どのような問題が出題されているのか、頻出問題ばかりなのでチェックするためにも利用すると良いでしょう。
とくにWEBテストは出題される問題の難易度もまばらなので、長文や四則逆算などが苦手な学生ほど使っておく事をおすすめします。
一応リンク貼っておくので、自由に使ってみてください。
WEBテスト問題集公式⇒https://careerpark.jp/
こちらの記事も参考にしてくださいね。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題6
グローバル化が進展する中で、企業に求められる経営能力は複雑さを増している。かつては製品やサービスの品質で差別化を図ることが中心だったが、現在では企業の理念や社会的責任、従業員への配慮といった要素も経営の重要な判断材料となっている。ブランドイメージの構築や社会課題への貢献といった側面が、消費者の選択基準としても無視できない存在となっている。
特に、従業員の多様性(ダイバーシティ)を活かす取り組みは、創造性や問題解決力の向上に寄与するとされ、国際的にも注目されている。ただし、その実践は容易ではなく、表面的な取り組みに終始してしまう例も少なくない。制度設計だけではなく、組織文化やリーダーの意識改革が不可欠とされており、形式的な導入では効果が限定的である。
さらに、社内での包括的な人材育成や、公正な評価制度の整備も多様性経営の鍵を握る。多様なバックグラウンドを持つ従業員が安心して力を発揮できる環境を整えることが、企業の競争優位性を高める手段となる。
また、ステークホルダーとの信頼関係を築くことも、持続可能な経営において重要視されるようになった。特に情報開示の透明性が問われる中で、経営層の説明責任はますます重くなっている。株主、顧客、従業員、地域社会など多様な利害関係者に対して誠実に対応することが、企業の長期的な成長には欠かせないと考えられている。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)現在の経営では、製品の価格が最も重視される指標である。
(2)ダイバーシティの推進は、制度設計だけで十分であると考えられている。
(3)ダイバーシティは、創造性や問題解決力の向上に貢献する可能性がある。
(4)経営層の情報開示に関する具体的な事例は、本文中に詳細に記載されている。
解答と解説を見る
(1)解答:B
本文では、製品やサービスの品質以外にも理念や社会的責任が重視されていると述べられており、「価格が最も重視される」とは書かれていない。
(2)解答:B
「制度設計だけでなく、組織文化やリーダーの意識改革が不可欠」と記載されているため、制度設計だけで十分とはいえない。
(3)解答:A
「ダイバーシティは創造性や問題解決力の向上に寄与するとされている」と本文に明記されている。
(4)解答:C
情報開示の透明性や説明責任については述べられているが、具体的な事例については本文に記載されていないため、論理的に導けない。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題7
近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業経営における重要なキーワードとなっている。DXとは、単に業務をデジタル化することではなく、デジタル技術を活用して企業のビジネスモデルや組織構造、価値提供の方法を根本的に変革することである。
多くの企業がDXを推進する背景には、顧客ニーズの多様化や競争環境の変化がある。従来の枠組みにとらわれず、スピード感を持って変化に対応するためには、従業員の意識改革やスキルアップも欠かせない。こうした変化に対応できる柔軟な組織づくりが、企業の成長を左右する。また、データを活用した業務プロセスの最適化や、顧客体験の向上もDXの目的の一部であり、単なるIT化ではない点が重要である。
一方で、DXの導入が進まない企業も少なくない。その要因として、既存システムとの整合性の問題や、社内の抵抗感、経営層の理解不足などが挙げられる。特に、現場と経営の間でビジョンの共有が不足している場合、取り組みが形骸化するリスクもある。成功には、明確なビジョンとリーダーシップ、全社的な取り組みが必要とされている。
DXは単なるIT導入ではなく、経営戦略そのものの見直しを意味しており、今後ますますその重要性は増していくと考えられる。今後の企業競争力を左右する中核的テーマとして、経営層と従業員が一体となって進めていく必要がある。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)DXとは、ビジネスモデルや組織の変革を伴う取り組みである。
(2)DXの推進には、従業員のスキルアップや柔軟な組織づくりが重要である。
(3)DXを進める上で、海外企業の動向を参考にすることが最も効果的である。
(4)DXの導入は、IT部門のみの取り組みで完結するのが理想である。
解答と解説を見る
(1)解答:A
本文冒頭に「ビジネスモデルや組織構造の変革」と記載があり、明確に正しい。
(2)解答:A
「スキルアップも欠かせない」「柔軟な組織づくりが成長を左右する」とあり、本文内容に一致する。
(3)解答:C
海外企業の動向についての記述は本文に存在せず、判断できない。
(4)解答:B
本文では「全社的な取り組みが必要」と述べられており、IT部門のみで完結するというのは誤り。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題8
サブスクリプションモデルは、近年さまざまな業界で注目されているビジネス手法のひとつである。従来の「モノを所有する」形から「サービスを利用する」形への価値観の変化により、定額制で継続的にサービスや商品を提供する仕組みが広がりを見せている。動画配信サービスや音楽配信サービスをはじめ、アパレル、家具、ソフトウェア、さらには食品や教育コンテンツまで、多岐にわたる分野で導入が進んでいる。
このモデルの魅力は、利用者にとっては必要なときに必要な分だけサービスを享受できる柔軟性、提供企業にとっては安定的な収益が見込める点にある。加えて、利用データを蓄積・分析することで、より個別最適化されたサービス提供が可能になり、顧客ロイヤルティの向上にもつながっている。
一方で、すべての事業においてサブスクリプションが万能というわけではない。たとえば初期投資が高額な商品や、購入後に頻繁な利用が期待されない製品には適していない可能性がある。また、継続的なサービス提供には、高品質な顧客対応やシステム整備が不可欠であり、運用体制の構築が課題となるケースも多い。
このように、サブスクリプションモデルは新しい価値提供の形として確立しつつあるが、適用には業種や顧客ニーズに応じた慎重な判断が必要とされる。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)サブスクリプションは、初期費用が高い商品に最も適しているビジネスモデルである。
(2)企業は利用者のデータを活用してサービスを最適化できる可能性がある。
(3)動画配信サービスにおけるサブスクリプションは、最も顧客満足度が高い業種である。
(4)サブスクリプションモデルは、適用には慎重な判断が求められる。
解答と解説を見る
(1)解答:B
本文では、初期投資が高い商品には必ずしも適していないと記載されている。
(2)解答:A
「利用データを蓄積・分析することで、個別最適化されたサービス提供が可能」とあるため正しい。
(3)解答:C
動画配信サービスにおける満足度についての記載はなく、判断できない。
(4)解答:A
「業種や顧客ニーズに応じた慎重な判断が必要」と明記されており、正しい。
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題9
企業におけるイノベーションの源泉として、近年「オープンイノベーション」の概念が注目を集めている。これは、自社のリソースにとどまらず、他社、大学、研究機関、さらには個人との協働によって新しい価値を創出する取り組みである。かつては社内での研究開発に重きを置く「クローズドイノベーション」が主流だったが、技術の高度化と市場の変化が早まる現代では、社外との連携によってスピード感と柔軟性を確保することが求められている。
オープンイノベーションの実践には、外部との関係構築や知的財産の管理、組織内の意思決定プロセスの柔軟化が必要であり、その導入には一定のリスクとコストを伴う。それでも、多様なアイデアや専門性を取り込むことで、企業は新たなビジネスチャンスを獲得し、競争力を高めることができるとされる。
実際、スタートアップ企業との協業や、オープンな技術コンテストの開催などを通じて、大企業が従来にはなかった発想を得るケースも増えている。一方で、こうした取り組みがすべて成功するとは限らず、成果を上げるためには明確な目的設定や進捗管理が欠かせない。
オープンイノベーションは一過性の流行ではなく、組織文化そのものを変革する取り組みとして、今後ますますその重要性を増していくだろう。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)オープンイノベーションは、主に大学ではなく政府との連携に特化した手法である。
(2)オープンイノベーションは、従来のクローズドイノベーションとは異なる発想である。
(3)オープンイノベーションを通じて企業が得る新しいビジネスチャンスは、競争力向上に寄与する。
(4)オープンイノベーションの取り組みは、すべてが成功しており、特別な管理は不要である。
解答と解説を見る
(1)解答:C
本文では大学との連携は触れられているが、政府との連携に特化しているとの記述はなく、判断できない。
(2)解答:A
「かつてはクローズドイノベーションが主流だった」とあり、オープンイノベーションはそれと異なる新しい考えであると読み取れる。
(3)解答:A
「新たなビジネスチャンスを獲得し、競争力を高める」と記載されており、本文に沿った正しい記述。
(4)解答:B
「すべて成功するとは限らず、明確な目的設定や進捗管理が欠かせない」と記載されており、誤りである。
また、今まさに出題されているWEBテストの練習ができると評判のアプリを紹介します。
このアプリはWEBテストの練習だけでなく、10段階評価で自分のWEBテストの偏差値も出してくれて、志望企業のボーダーを突破できるのかも分かる便利アプリです。
この問題と「無料で手に入るWEBテストの問題集」だけやっておけばWEBテストは安心なので、スマホでこのページを見たこの機会に是非「WEBテストの練習ができると評判のアプリ」と「無料で手に入るWEBテストの問題集」を試してみてくださいね。

こちらのURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!そしてWEBテストのボーダーを突破しましょう!
※PCでご覧の場合は、URLをクリック後にお手元のスマホでQRコードを読み込んでくださいね。
URLはこちら⇒https://lognavi.com/
\ 先ずはインストール /
もしWEBテストに自信が持てない場合は、選考対策をサポートしてもらえる「キャリタス就活エージェント」を利用すると良いでしょう。

「キャリタス就活エージェント」では厳選された企業、外資系企業やグローバル展開する優良企業の非公開求人なども紹介してくれるので、驚くような企業の内定も期待できます。
専任のキャリアアドバイザーが応募書類や面談に対する対策もしてくれるので、1人で選考対策をするよりも内定率の向上も望めるので、選考対策に悩みがある場合は必ず相談してみましょう!
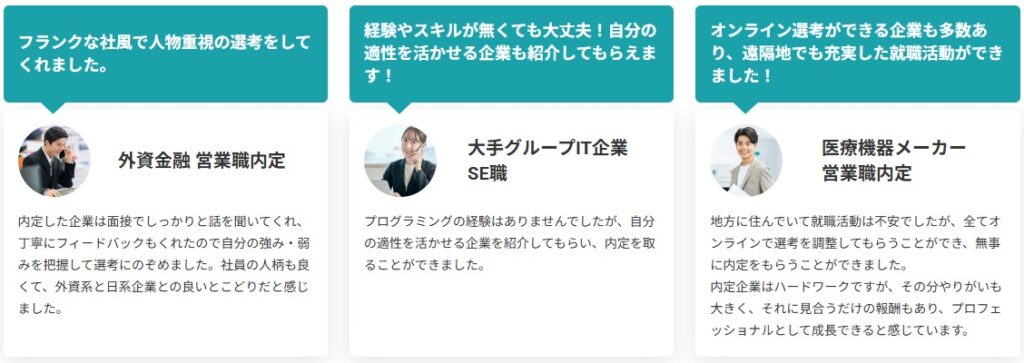
「キャリタス就活エージェント」は全て無料で完結できるので、これから内定が少しでも早く取りたい場合は是非利用してみてくださいね。
公式ページ⇒https://agent.career-tasu.jp/
\ 登録は30秒で完了 /
玉手箱試験の論理的読解の過去問・練習問題10
近年、働き方改革の一環として「ワーケーション」という新たな勤務スタイルが注目を集めている。これは「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語であり、観光地やリゾート地など、通常の職場とは異なる場所で仕事を行うことを指す。テレワークの普及とともに導入が進み、企業や自治体による支援施策も増加している。
ワーケーションの導入には、従業員のリフレッシュや生産性の向上、地域との新たな関係構築といった利点があるとされる。特にクリエイティブな業務においては、環境の変化が新たな発想を生む要因になることもある。一方で、業務と休暇の線引きが曖昧になりやすく、労働時間の管理や成果評価の基準が不明瞭になるといった課題も指摘されている。
さらに、すべての職種に適応可能というわけではなく、顧客対応や機密性の高い情報を扱う業務では導入が難しいケースもある。また、通信環境や宿泊施設の整備状況によっては、業務に支障をきたすこともある。
ワーケーションは万能な働き方ではないが、従来の勤務形態に柔軟性を持たせる新たな選択肢として、今後も議論が進められていくことが期待されている。
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)ワーケーションは、休暇中は一切仕事をしないという制度である。
(2)ワーケーションは、特に創造的な業務において効果が期待されている。
(3)ワーケーションはすべての職種にとって適用可能である。
(4)ワーケーションには労働時間や成果評価に関する課題も存在している。
解答と解説を見る
(1)解答:B
本文では「仕事」と「休暇」を組み合わせる働き方とあり、「一切仕事をしない」は誤り。
(2)解答:A
「クリエイティブな業務においては、環境の変化が新たな発想を生む要因になる」と記述されている。
(3)解答:B
「すべての職種に適応可能というわけではない」と明記されており、誤りである。
(4)解答:A
「労働時間の管理や成果評価の基準が不明瞭になる課題がある」と本文にあり、正しい。
スマホでこのページを見ている方限定でお伝えしたいのが、今まさに出題されている玉手箱の問題が出ると評判の「Lognavi」というアプリです。
MBTI顔負けの性格診断も出来て、あなたの市場価値まで企業側に伝わって超大手優良企業からのオファーももらえちゃうから一石二鳥です!

下記のURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!
自分の玉手箱の出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。
アプリインストールはこちらから⇒https://lognavi.com/
※インストール後の初回起動はお早めに
\ 先ずはインストール /
ESや企業研究で玉手箱に時間を割く暇がないと思うので、今選考で出題されている玉手箱の練習が無料でできる玉手箱の無料問題集をやっておいてください。
無料でダウンロードできるので、玉手箱に時間をかけたくない場合は使ってみてください。
▼25卒に大人気でした▼
参考書や問題集と違って問題が最新版にアップデートされるので、今どのような問題が出題されているのか、頻出問題ばかりなのでチェックするためにも利用すると良いでしょう。
とくにWEBテストは出題される問題の難易度もまばらなので、長文や四則逆算などが苦手な学生ほど使っておく事をおすすめします。
一応リンク貼っておくので、自由に使ってみてください。
WEBテスト問題集公式⇒https://careerpark.jp/
こちらの記事も参考にしてくださいね。
玉手箱の論理的読解以外についてはこちらの記事を参考にしてください。
- 玉手箱の計数(非言語)のコツと無料練習問題!35分どっちでも解答・答えを出す方法
- 玉手箱の英語を無理と思わず対策しよう!解答集つき練習問題を公開
- 法則性テストは玉手箱じゃなくCAB!解答集や解き方・練習問題と答えについて解説
- 玉手箱の四則逆算のコツ!アプリや自動計算は?時間足りない問題を解消する方法
- 玉手箱【言語】練習問題と答えや解説を無料公開!例題やコツを参考にしよう
- 【玉手箱】図表の読み取りができない時の例題や練習問題を公開!コツを掴もう
- 玉手箱【表の空欄の推測】練習問題とコツを公開!できないとヤバイ?
玉手箱の論理的読解を解くコツを知れば難しい苦手意識がなくなる
玉手箱の言語問題に初めて触れたとき、私は正直なところ「国語が苦手でなければ何とかなるだろう」と考えていました。大学受験でそれなりに現代文を解いてきた経験もあり、文章を読むこと自体には抵抗がなかったからです。
文章は確かに日本語で書かれていますが、求められているのは感想や解釈ではなく、書かれている内容をそのまま論理的に処理する力です。しかも、制限時間が非常に厳しく、丁寧に読み込む余裕はありません。
ここで私は、玉手箱の言語問題は「国語の読解」ではなく、「論理情報の取捨選択」だと認識を改める必要があると気づきました。
この認識の転換ができるかどうかで、玉手箱の言語問題に対する向き合い方は大きく変わります。私はこの転機を境に、読み方と練習方法を根本から見直しました。
論理的読解で最も重要なのは「筆者の主張を探さない」こと
一般的な国語の読解問題では、「筆者の主張は何か」「筆者の考えとして最も適切なものを選びなさい」といった設問が多く出題されます。そのため、多くの学生は無意識のうちに、「この文章で一番言いたいことは何だろう」と考えながら文章を読み進めてしまいます。
しかし、玉手箱の言語問題、特に論理的読解では、この読み方が大きな落とし穴になります。なぜなら、玉手箱では筆者の主張や意図を推測する必要がほとんどなく、文章中に書かれている事実関係や論理関係だけを正確に把握できれば十分だからです。
私が最初につまずいたのも、この点でした。文章の流れやニュアンスをつかもうとするあまり、余計な解釈を加えてしまい、設問で問われている「正しいか・誤っているか」という判断を誤っていました。練習を重ねる中で、私は「書いていないことは考えない」「書いてあることだけを見る」という姿勢を徹底するようになりました。
文章は「理解する」のではなく「条件として扱う」
玉手箱の論理的読解では、文章はストーリーとして味わうものではなく、条件が並んだ説明文として扱う意識が重要です。私はこの考え方に切り替えてから、読むスピードと正答率の両方が安定しました。
この読み方を意識すると、文章の長さに対する心理的な負担が大きく減ります。長文であっても、「条件がいくつ並んでいるか」という視点で見ると、意外とシンプルな構造になっていることが多いのです。私は練習問題を解く際、文章を読んだ後に「今、条件はいくつあったか」と頭の中で確認するようにしていました。
接続詞と限定表現だけを意識して読む練習が効果的だった
論理的読解で特に重要なのが、接続詞や限定表現です。「しかし」「一方で」「つまり」「ただし」「必ずしも〜とは限らない」といった言葉は、文章の論理構造を大きく左右します。
私が行っていた練習方法の一つに、「接続詞だけを拾いながら読む」というものがありました。最初は極端に感じるかもしれませんが、この練習をすると、文章の骨組みがはっきり見えるようになります。細かい説明や具体例は一旦置いておき、論理の流れだけを追うのです。
玉手箱の論理的読解では、この論理の流れさえ追えていれば、設問の多くは解けてしまいます。逆に、細部にこだわりすぎると時間を失い、全体を見失ってしまいます。私はこの練習を通じて、「全部読まなくていい」という感覚を体に覚えさせました。
選択肢は「本文と一致するか」だけで判断する
玉手箱の言語問題では、選択肢が一見もっともらしく書かれていることが多く、つい「こちらの方が正しそうだ」と感覚で選んでしまいがちです。しかし、論理的読解においては、その感覚はほとんど役に立ちません。
逆に、表現が言い換えられていても、本文の内容と論理的に同じであれば正解です。
この判断を素早く行うためには、練習段階で「本文のどの一文と対応しているか」を意識することが重要です。私は練習問題を解いた後、正解の選択肢が本文のどこに根拠を持っているのかを必ず確認していました。
練習問題は「解き直し」より「読み直し」を重視した
玉手箱の言語問題対策で、多くの人がやりがちなのが、間違えた問題を何度も解き直すことです。しかし、私の経験上、論理的読解に関しては、解き直しよりも文章の読み直しの方が効果的でした。
なぜ間違えたのかを振り返ると、多くの場合、「読み落とし」「条件の勘違い」「書いていないことを補ってしまった」という原因に行き着きます。
この作業を繰り返すことで、自然と「やってはいけない読み方」が身についていきました。論理的読解は、知識を増やすよりも、誤った思考癖を減らすことが重要だと感じています。
無料アプリで「形式」と「判断スピード」を鍛えた経験
玉手箱の言語問題対策として、私は無料アプリも積極的に活用しました。無料アプリの最大の利点は、短時間で多くの問題に触れられる点です。論理的読解では、判断スピードが非常に重要になるため、この反復練習が大きな意味を持ちました。
アプリでの練習では、完璧な理解を目指すのではなく、「素早く判断する感覚」を養うことを意識していました。最初は正答率が安定しなくても、繰り返すうちに「この選択肢は本文に書いていないから違う」と瞬時に判断できるようになりました。
このスピード感は、紙の問題集をじっくり解くだけではなかなか身につきません。玉手箱の論理的読解では、反射的な判断力が重要であり、それを鍛えるにはアプリでの反復が非常に効果的でした。
本番で実感した「論理的に読む癖」の効果
実際に玉手箱の本番を受検したとき、私は以前ほど文章の長さに圧倒されることはありませんでした。文章を見た瞬間に、「条件は何か」「例外はあるか」「設問はどこを聞いているか」という視点で、自然と頭が動いていたからです。
結果として、焦らずに判断でき、時間配分にも余裕が生まれました。特別なテクニックを使ったというよりも、論理的に読む癖が身についていたという感覚でした。この状態を作れたことが、玉手箱の言語問題を安定して乗り越えられた最大の理由だと感じています。
玉手箱の論理的読解は難しいと思い込まない事が大切
玉手箱の言語問題における論理的読解は、センスや国語力で決まるものではありません。正しい読み方を知り、それを繰り返し練習することで、誰でも確実に上達します。
もし今、玉手箱の言語問題に苦手意識を持っているのであれば、それは能力の問題ではなく、読み方の問題です。正しいコツと練習方法を意識すれば、必ず克服できる分野だと、私の体験から自信を持ってお伝えします。
- 今選考で出題されている問題が出る!「Lognavi」
「Lognavi」は今企業の選考で出題されている玉手箱の問題が出ると評判のアプリで、玉手箱の偏差値も出せるので、自分のレベルを知るためにも利用する価値があるアプリです。
Lognavi公式はこちら⇒https://lognavi.com/
- 最新の玉手箱を何度でも練習できる!「キャリアパーク」
「キャリアパーク」のWEBテストパーフェクト問題集は最新の玉手箱の問題が200問あり、解答や解説もついているので非常に学びになる無料の問題集です。
玉手箱の解答集つき問題集公式⇒https://careerpark.jp/
玉手箱の論理的読解は難しい?過去問や練習問題を公開まとめ
玉手箱試験の論理的読解の過去問や練習問題は参考になりましたでしょうか。
玉手箱試験の論理的読解は文章が長文な事もあり、短時間で解いていくのは容易ではありません。
とにかく何回も繰り返し練習をする事でコツを掴んでいきましょう。
問題は最新版を追記・または問題の入れ替えを随時行うので定期的にチェックしてみてくださいね。
玉手箱試験を開発した日本エス・エイチ・エル株式会社の企業情報
| 会社名 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 奈良 学 |
| 設立年月日 | 昭和62年12月22日 |
| 資本金 | 資本金 656,030千円(2022年9月30日現在) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8-0104-0117-1621 |
| 本社所在地 | 〒164-0011 東京都中野区中央五丁目38番16号 STNビル |
| 新宿オフィス24階 | 〒163-1524 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 新宿エルタワー24階 |
| 新宿オフィス6階 | 〒163-1506 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 新宿エルタワー6階 |
| 名古屋オフィス | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南ニ丁目14番19号 住友生命名古屋ビル19階 |
| 大阪オフィス | 〒530-0057 大阪市北区曽根崎二丁目12番7号 清和梅田ビル14階 |
| 取締役 | 代表取締役 奈良 学 取締役 三條 正樹 取締役 中村 直浩 (監査等委員) 取締役 神田 貴彦 取締役 朝日 義明 取締役 岡太 彬訓 |
| 執行役員 | 清田 茂 縄間 重之 重原 公 |
| 従業員数 | 116名(2022年9月30日現在) |
| 平均年齢 | 35.1歳(2022年9月30日現在) |

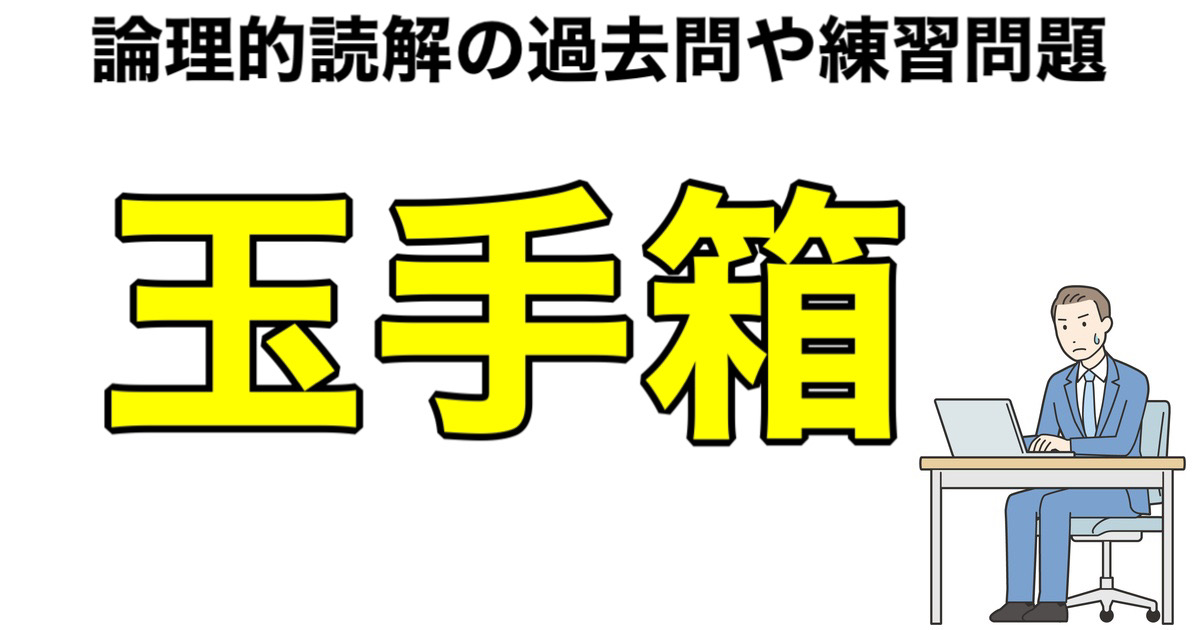

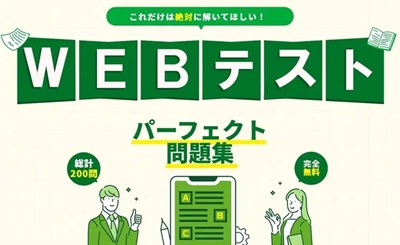


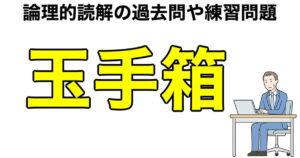

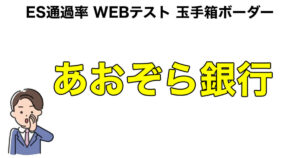

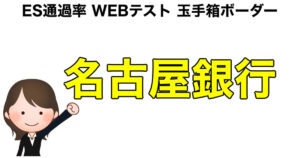

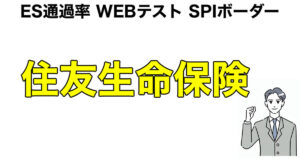
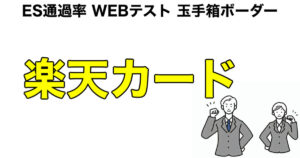
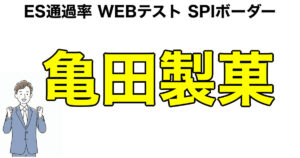

コメント